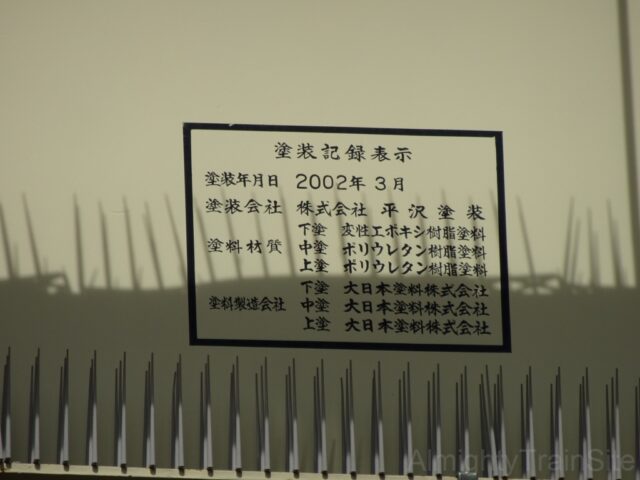今回は2025年4月5日をもって廃止された「東京高速道路」の走り納めを主とした活動をしました。
当ブログは鉄道ブログであり、バスを取り上げることはままありましたが、道路を主題とする記事を書くのはこれが初めてではないかと思います。
この東京高速道路は路線バスなども設定されておらず、歩行者や自転車、原付の乗り入れは禁止されているため、体験するならば自動車かバイク(自動二輪)を使うしか無く、マイカーを持たない私はカーシェアリングを利用してこの活動に臨みました。
今までにも駅めぐりとか沿線での撮り鉄のためにレンタカーを利用したことはありましたが、道路を走るためだけに借りたのは今回が初めてですねw
また、東京高速道路と接続しており、同日より10年間通行止めとなる首都高速八重洲線についても合わせてレポートしていきたいと思います。
東京高速道路と八重洲線について
まずはこの記事の主題となる東京高速道路と八重洲線について解説してから本題に入っていくとしましょう。
東京高速道路は東京高速道路株式会社が運営する一般自動車道で、一般的には「KK線」と呼ばれることもあります。
一般自動車道というのは道路運送法に基づく道路の種類の1つであり、大雑把に言えば民間企業が運営する営利目的の道路ということができるでしょう。
観光地によくある「◯◯スカイライン」とか「◯◯パークウェイ」といった道路は大抵これであり、収益を目的としている点からも通常は有料道路として運営されることになります。(ちなみに、一般自動車道の仲間として専用自動車道というのもありますが、こちらは運営会社自らの車両を通行させるために運営される自動車道であり、バス会社が設置するバス専用道路が典型例ですね。)
しかし、東京高速道路の珍しい点は一般自動車道でありながら通行料を徴収しない運営形態となっていることであり、「無料で通れる高速道路」としても知られていました。
民間企業が運営しているのにどうやって通行料無料で事業が成り立っているのかというと、道路の下にテナントを入居させており、その賃料で道路の維持費も賄っているのです。
これは河川の上に道路を建設しており、公共の河川を利用する条件として通行料を徴収しない事を条件とされたためだそうです。
路線としては汐留乗継所~白魚橋乗継所間のおよそ2kmほどの路線で、途中の西銀座JCTで八重洲線と分岐します。
また、汐留乗継所でも八重洲線(南側)と接続し、都心環状線と接続するほか、白魚橋乗継所では都心環状線の支線と接続していました。
このように2km程度の短い路線でありながらも3箇所で首都高速と接続しており、事実上首都高速と一体的な交通ネットワークを形成していたことになります。
立地的には八重洲線と連携して、都心環状線のバイパスルートとしても活用でき、実際そういう目的で通行する利用者も少なくなかったようですが、その際には通行料についての特例があり、東京高速道路を経由して八重洲線や都心環状線を連続走行する場合は、全て首都高速を経由した場合と同等の通行料となるように調整されるようになっていました。
歴史としては1959年に最初の区間が供用開始されており、何気に首都高速よりも長い歴史を持っていたりします。
続いて八重洲線についてですが、こちらは首都高速の一部であり、都心環状線西神田JCTから分岐して汐留JCTで再度都心環状線に合流するという路線ですが、途中に東京高速道路を挟んでいるため西神田JCT~西銀座JCT間と汐留乗継所~汐留JCT間の2区間に分かれています。
東京高速道路と一体になり都心環状線のバイパスルートとして機能するほか、八重洲地区へのアクセスも提供していました。
面白い施設として八重洲出入口があり、こちらは出入口とはいうものの一般道とは直結しておらず、その代わりに駐車場に繋がっていて、駐車場を通り抜けて一般道に出ることも出来ますが、その場合は通行料の他に駐車料金も必要だったりします。
その他、乗客を下ろす目的に特化した「八重洲乗客降り口」という施設もあります。
これもレポートしていこうと思います。
そんな東京高速道路と八重洲線ですが、東京高速道路については2025年4月5日をもって廃止(※厳密には白魚橋乗継所~東銀座出口のみ存続)され、八重洲線は同日より10年間通行止めとなります。
この理由ですが、これは都心環状線の一部地下化に伴うもので、現在は西神田JCTから高架で江戸橋JCTまで向かっている都心環状線ですが、これを地下化し、日本橋付近の高架橋を撤去して日本橋上空の景観を取り戻そうという目的もあるようです。
しかし、これに際して江戸橋JCTでは都心環状線京橋方面と西神田JCT方面への接続路が廃止されることとなり、江戸橋JCTでは従来通り都心環状線を通行することができなくなります。
この代替として八重洲線の一部を都心環状線に組み込んだ上で、丸の内~新富町間に新たな地下トンネル「新京橋連絡路」を整備し、八重洲線とともに新たな都心環状線のルートとなります。
西神田JCTから6号向島線方面へは八重洲線の途中から分岐する新たな地下トンネルによって接続し、京橋方面から1号上野線と6号向島線へは従来の都心環状線をそのまま活用するようです。
これにより八重洲線から都心環状線への連絡ルートとしての役割は東京高速道路から新京橋連絡路に移管されることとなり、東京高速道路は役目を終えることになったのです。
東京高速道路を改築して都心環状線に組み込む構想もあったようですが、急カーブがあり大型車が通行できない環境から東京高速道路を廃止して新たな地下トンネルルートを整備することになったようです。
なお、前述の通り東京高速道路は道路の下にあるテナントの賃料で運営しているため、道路が廃止になっても会社の経営には影響はないようです。
それでは説明はこれくらいで本編に入りましょう。
東京高速道路
まずは東京高速道路を見ていきます。
前半は徒歩で出入口などを見学し、後半ではカーシェアリングを借りて実際に本線を走行していきます。

見えてきました。
東京高速道路は屋上部分が道路になっている建物と、一般道と交差する部分の架道橋からなっており、架道橋にはそれぞれ名前がついています。
写真は「銀座新橋」という橋です。

入口です。
新橋出入口という入口であり、昭和通りに接続しています。

上部には首都高速の入口にもある歩行者・自転車の進入禁止を知らせる看板が、下部にはKK線の廃止を知らせるお知らせも出ています。

規制標識の数がすごいですねw
これを一瞬で理解できる人がどれくらいいるんだという気もしますが、トラック、バス、ミニカー、小型特殊車と小型自動二輪は通行禁止であり、二輪車の二人乗りは禁止ということですね。

特定中型以上禁止とありますが、特定中型というのは中型自動車に含まれる車両のうち、一定以上の条件を満たす車両の区分であり、中型免許ができる以前の大型車に相当する車両が当てはまるようです。
中型免許を持っていれば特定中型もそれ以外の中型も運転できますが、2007年以前に取得した普通免許は現在では8t以下限定中型免許として扱われており、これで運転できるのは特定中型でない中型車のみとなります。

入口の案内です。
自動車道入口とあり、これは前述の通り東京高速道路が自動車道事業に基づく道路であることを示しています。
また、道路名と入口名も書いてありますが、短い路線ながらナンバリングもされているんですね。
あと、路線番号もありますが、東京高速道路が運営するのは1路線だけなのに「D8」なんですね。
詳しくは後述しますが、白魚橋乗継所で接続する首都高速が正式には「首都高速8号線」と呼ばれているため、これにならったんでしょうか。
それではここからはカーシェアを借りて実走といきましょう。
↑車載動画をどうぞ!
新橋出入口から流入し、新京橋出口まで走行します。

スクショでもご紹介していきます。
ここからは車窓視点から御覧いただきましょう。
ランプを登って本線へ上がっていきます。

本線に合流です。
加速帯の短さも特徴的ですが、首都高速でもここまで短いところはそうそうないでしょう。

本線に合流するとすぐに片側1車線に収束します。
地方ならばこういう構造の高速道路もあるでしょうが、KK線は大都会にある対面通行の高速道路という点でネタ度が高いですね。(前述の通り、KK線は正式な意味での高速道路ではありませんがw

すぐに急な右カーブです。
このカーブの存在が大型車の通行を妨げているんでしょうか?

カーブを過ぎると東海道新幹線との併走区間ですが、生憎新幹線は通りませんでしたw
こんなところに路上駐車して出待ちをするわけにもいかないので完全に運ゲーですね。

大都会のビル群を見上げながら走る光景はKK線ならではですよね。
これを車に乗りながら楽しめるのはこれが最後でしょう。

車線は2車線に増えます。
左は八重洲線へ分岐する方で、右の上野方面が本線となります。

左の料金所は八重洲線に向かう道であり、ここから先は首都高速なので当然通行料が必要です。

また右カーブです。
首都高速もカーブが多いですが、KK線のそれは卓越していますね。

スロープを降りるといきなり町中に出て一時停止を求められるなど、高速道路という名前とのギャップを感じる構造ですね。
といったところで5分に満たないさよなら通行は終わりですが、せっかくカーシェアリングを利用してまで走りに来たわけですから、もう少し走ります
というわけでさよなら通行のおかわり!
↑というわけで車載動画の第2弾です。
今度は一度首都高速に流入して、首都高速経由でKK線へ向かいます。

まずは首都高速都心環状線上からスタートです。
3車線のうち一番右側がKK線へ向かう車線ですが、廃止直前ということで行先案内の路面標示は既に消されていました。

分岐の標識が出てきました。
標識にKK線の文字はありませんが、東銀座や新橋といった地名が案内されていますね。

対向車線にはKK線から合流するランプウェイが合流してきていますね。
ちなみに、余談ですが、都心環状線と分岐する京橋JCTからKK線との接続点となる白魚橋乗継所までの区間は正式には首都高速8号線という独立した路線なのです。
しかし、その距離わずかに100m程度と極端に短い上、実質的には都心環状線とKK線を結ぶランプウェイとしてのみ機能しているという実態から、正式名で案内されることはほとんどなく、実質的には都心環状線の支線として認識されています。
なぜそのような短距離の路線が首都高速として建設されるに至ったのかというと、そもそもKK線として建設された区間も元々は首都高速の一部として建設される計画だったからです。
結局はKK線区間は首都高速とは別の会社の自動車道として建設されることとなり、首都高速とKK線を連絡するわずかな区間のみを首都高速として建設することになり、これに8号線という路線名が与えられたという経緯があります。
しかし、8号線はそもそもKK線との接続ありきの路線でしたからKK線とともにその歴史に幕を下ろすことになります。
が・・・実は完全に廃止になるかというとそうではなくて、KK線の新橋方面にある東銀座出口のみ存続し、わずか120mほどではありますが、KK線の本線も一部が存続するため、これに接続する目的で8号線も都心環状線から白魚橋乗継所の方向のみ存続し、今後は都心環状線の出口ランプとしての機能に特化する形で活躍することになります。

いよいよ分岐地点となる京橋JCTです。
とうとう8号線という案内を見ることはありませんでしたw

そうして始まった8号線区間ですが、どこからどう見てもただのランプウェイですねw

かつての川底を走る都心環状線と高架のKK線との高低差を埋めるためにぐんぐん登っていきます。
首都高速ではこれくらいの勾配は珍しくないですが、短い路線の大半が勾配だと考えると8号線の異質感が増しますね。

東銀座出口の案内が出てきました。
KK線廃止後は東銀座出口が唯一のこの道路の目的地となります。

乗継所の案内も出てきました。
乗継所とはKK線と首都高速の境界に設けられている施設であり、実質的には料金所ですが、KK線を経由して10分以内に再び首都高速に再流入した場合は通行料を通算する特例がありました。
鉄道でいうところの通過連絡みたいな感じですね。
現金車はここで乗継券というのを受け取り、再流入時にそれを提示すると通行料を通算する取り扱いを受けられましたが、ETC車はノンストップで通過可能で、自動的にこの特例が適用されていました。

こちらが乗継所です。
まあ、特例的な運用がされる以外は、ごく普通の料金所ですけどねw
なお、KK線廃止後はこの特例も当然廃止になるため、この料金所は都心環状線の出口としての役割のみとなる予定です。

東銀座出口です。
ここから先が名実ともに廃止となる区間であり、走り納めとなります。
廃止後は出口のみが存続し、本線を直進することはできなくなります。

見納めとなるKK線を進みます。
先程も見た景色ですが、方向が違うとまた違って感じられますね。

2車線道路に収束します。
都心環状線にこんな場所があったら渋滞の名所となっていることでしょうが、KK線はそこまでの交通量はないのか渋滞したという話はあまり聞きませんね。

合流してきたのは八重洲線から合流する西銀座乗継所/西銀座JCTです。
八重洲線は廃止されず、都心環状線の新ルートとして活用されることになっていますが、新ルートは地下トンネルで京橋へ繋がる計画であり、地上へ繋がる部分は廃止されるようです。

八重洲線と合流して新幹線との並走区間です。
ここでドクターイエローでも見られたら一生分の運を使い果たすレベルの幸運ですね。

新橋出入口への分岐の案内です。
ここがKK線内で流出できる最後の出口であり、ここを過ぎると汐留乗継所で汐留乗継所に入っていきます。
つまりは、通行料を払いたくない人はここまでですw
ただし、現地にはそれらしい案内がないので、首都高速を利用するつもりがなかったのに間違えて直進してしまうというのは結構あるあるだったのでは?w

もう少しKK線は続きますが、前述の通りこれより先は首都高速に流入するしかないので、実質的には有料区間となります。

料金所の案内です。
案内標識の背景が緑になっているので、既にこの区間は首都高速なんでしょうね。
ちなみに、汐留乗継所から汐留JCTまでの区間は八重洲線の一部として扱われており、このため八重洲線はKK線を挟んで2区間に分断されていることになります。
KK線が大型車も通行できる規格だったらKK線を買収して八重洲線に組み込むという可能性もあったでしょうが、さすがに大型車が通れない道路を首都高速にするわけにはいかなかったのでしょうか。
なお、八重洲線の南側区間もKK線と同時に廃止される予定です。

汐留料金所です。
KK線からやってきた車両と汐留出入口から流入してきた車両の両方を受け持つ料金所ですが、KK線廃止後は汐留出入口への料金所としてのみ利用されるようです。

都心環状線と合流する地点が汐留JCTとなります。
KK線、及び八重洲線南側の廃止後はジャンクションではなくなり、汐留出入口へのランプウェイとなる予定ですが、施設としては特に変化はなさそうです。
といったところで2回目の走行は終わりですが、今度は八重洲線も走るため、3回目の走行へ向かいます。
ただ、ここから近くには意外と出入口がなく、芝公園まで行ってから戻ってくることに・・・
↑というわけで3回目の車載動画です。
今度は都心環状線からKK線を経由して八重洲線へ向かいます。

芝公園まで行ってから折り返してきまして、再び都心環状線の本線上から再開です。
路線名の表示がなかった8号線とは違い、八重洲線の標識もちゃんと出ていますね。
もっとも、多くの利用者は西銀座JCTから先が八重洲線であって、汐留JCTから直接KK線が始まると思っている人が多そうです。

いかにも首都高らしい急カーブですが、3車線のうち一番左は汐留出口とKK線方面の車線となっており、しかも汐留出口方面から本線へは進路変更が出来ないので、都心環状線を連続走行する場合は真ん中か右側の車線を走行する必要があります。

汐留JCTです。
ここも汐留出口として存続するはずですが、標識の内容は書き換えられることでしょう。

KK線に入りました。
自動車道入口の標識があるので分かりやすいですね。

続いて現れたのは土橋入口です。
京橋方面への入口のみとなっており、加速帯の短さが特に顕著ですね、
タイミングが悪いと合流できなさそうですが、本線も40km/h規制なので最悪停まってしまっても本線の交通が途切れるのを待てばなんとかなりますかね。

新幹線との併走区間開始です。
が、今度も新幹線は通らず・・・

もうすぐ西銀座JCTです。
今度は八重洲線へ向かうので左車線を進みます。
八重洲線方面は北池袋方面と案内されていますね。

ゲートを過ぎるとすぐに下り坂となり地下トンネルへ向かいます。
八重洲線の大半が地下なので、地上区間は貴重です。
10年間の通行止め後は新たな地下ルートで京橋へ至る予定なので、この地上区間は見納めとなる可能性が高いでしょう。

トンネルに入りました。
今は地下を走る道路も珍しくなくなっていますが、八重洲線はその初期の例ですね。

駐車場と案内されているこちらは八重洲出入口です。
地下にあるインターチェンジも今では珍しくないですが、八重洲出入口の珍しい点は「一般道とは直接接続していない」という点です。
ではどこに繋がっているのかというと地下駐車場です。
それではここはパーキングエリアなのかというとそうでもなく、駐車場自体は一般道からも利用可能です。
つまりは首都高からも一般道からも利用可能な有料駐車場であり、駐車場を経由すれば一般道へ出ることも可能です。
ただし、その場合は首都高の料金だけでなく駐車料金も発生します。
間接的には一般道へも出入りできるので出入口として扱われていますが、案内上は駐車場と呼ばれているようですね。
2025年現在、このような形態の首都高速の出入口は八重洲出入口だけですが、2016年までは常盤橋出入口という施設が同じく駐車場にのみ接続する出入口でした。

車線は1車線ですが、トンネル自体は2車線分確保されているようです。
都心環状線の新ルートとして活用される際は、6号向島線方面へのトンネルへの分岐がこのあたりに作られる予定ですが本線部分はそのまま活用できそうですね。

左へ分岐する車線は廃止された常盤橋出入口への分岐でしょうか?

トンネルを抜けると急な上り坂で高度を上げて都心環状線の高架へ取り付いていきます。
この区間の高架は最終的に地下ルートへの切り替えで撤去される予定なので、この付近の景色も大きく変わることでしょう。

神田橋JCTで都心環状線に合流ですが、ここで渋滞発生!w
まあ、ここはいつも混んでいるイメージありますしね。
といったところで3回目の走行は終わりですが、最後に八重洲線を逆方向に走行するとともに、”あの名所”へも行ってみたいと思います。
↑というわけで適当なところで引き返して、最後に八重洲線→KK線と走行していきます。

続いては都心環状線外回りからスタートです。
神田橋JCTから八重洲線へ分岐していきます。
都心環状線は渋滞していますが、八重洲線はスムーズであり、八重洲線とKK線の渋滞回避ルートとしての価値を実感する光景です。
KK線廃止と八重洲線長期通行止めが都心環状線の混雑にどう影響するのかは気になります。

先ほどとは逆に急な下り坂で地下トンネルへかけ下っていきます。
都心環状線の高架を見渡せる光景も見納めです。

トンネルが出てきました。
こちら側も1車線で供用されていますが、トンネルは2車線分ありますね。

ここで一旦本線を外れます。
といっても八重洲出入口で降りるのではなくて、八重洲線名物の”アレ”を見に行きます。

左へ行くと駐車場であり、よくあるコインパーキングのゲートがありまして、そこで駐車券を受け取るとともに首都高の通行料を精算します。
一方、直進すると「八重洲乗客降り口」という施設があります。

こちらが八重洲乗客降り口です。
名前の通り、乗客を降ろすためだけの施設であり、乗用車2台ほどが停車可能なスペースが設けられています。
ここを利用するだけならば首都高の料金所を通過しなくていいので東京駅やその周辺に人を送り届ける場合はここで降ろせば首都高を降りないで済みます。
なお、あくまで”降り口”なので、反対にここから乗せることは出来ないのですが、迎えに来る場合は八重洲出入口を利用して駐車場に停めてから待つということになります。
ここで降ろされた人は通路を経て八重洲地下街へ抜けることが出来ますが、八重洲地下街側からは扉を開けられないようになっているので、八重洲地下街からここを訪れることは出来ません。
東京駅にも近い便利な立地ですが、その存在は意外と知られておらずマイナーな存在ですよね。
また、裏技的な利用方法としてタクシーに乗車してここを目的地に指定することでよりスムーズに東京駅へアクセスできるというのもありますが、その場合は降車の時点では首都高の料金を精算していないので手計算で料金を算出してから運賃を決定しないといけないようです。
ここも八重洲線の通行止めに合わせて10年間利用できなくなりますが、廃止されるわけではないようなので再開後はまた活躍しますね。
ここではせっかくなので車を降りて手短にではありますが見学していきましょう。
後続車があれば車内からの見学に留めようと思っていましたが、幸いにして後続車はないようです。

というわけで車外から見学です。
何も知らなければ路上駐車しているようにしか見えないですが、首都高では唯一合法的に停車できる場所となっています。

こちらが地下街へ抜ける通路です。
前述の通り、降り口から地下街への一方通行であり、地下街からこちらへは来られないので、ここで降りる人以外はこの扉を通ってはいけません。
見送りや見学で訪れた人がここを通過してしまうと戻ってこられなくなって、最悪クルマだけここに取り残されることになりますからね。

もう少し引きで
一応矢印で案内されていますが、歩行者がいたらいけない場所にいるような罪悪感がありますw

車道側はラバーコーンがこれでもかと敷き詰められていました。
このまま車道を進めば首都高の本線になってしまうので、歩行者の誤進入は防がねばなりませんからね。

降り口の案内標識です。
やはり乗車はできないという注意書きがありますね。

不法駐車監視中とありますが、ここで不法に乗客を待つ不届き者に対する警告でしょうか?
ドアは向こう側からは開けられないとは言え、携帯が普及した現代ならば到着したら連絡してもらって、こちら側から開けるとかやりようはあるでしょうしね。

貼り紙でも警告されていました。
2台分しかスペースがないので、長時間停車されると死活問題なんでしょう。

後方からもう1枚
ちなみに、前方に停車しているクルマの方も見学目当てで訪れた人のようで、写真を撮ったりされていました。
それではそろそろ撤収です。
合法的に停車できるとは言え、長居は一般の利用者へのご迷惑になりますしね。

右手に分岐するのは丸の内出口です。
八重洲線では唯一の一般道へ直接接続する出口ですが、神田橋JCTから西銀座JCTの方向にのみ利用可能です。

ゲートを通過したら車載シリーズも〆たいと思います。
このあとはカーシェアを返却して、歩きながらKK線を見学したいと思います。

こちらは新橋出入口の出口です。
ビルにランプウェイが併設されているようにも見えますね。

歩行者・自転車の誤進入を防ぐ看板類
何気にKK線を意味する”TOKYO EXPRESSWAY”とも書かれていました。

高架下は銀座ナインという名前の施設になっています。
前述の通り、KK線の維持費用はテナント料で賄われていました。

商業ビルからKK線を見下ろしてみました。
見上げる構図だと歩行者空間へ転用されたあともあまり変化はないでしょうが、自動車が走行している光景はもう見納めですからね。

最後にゴジラに壊されることに定評のある和光を撮ったら撤収です。
これにてKK線と八重洲線の走り納めは終わりですが、実は別の形でもう1度KK線に関わることになったのでした。
それは別記事として追ってレポートしますので、公開までしばらくお待ち下さい。
~追記~
そのレポートはこちら!
それでは!
あわせて読みたい関連記事
- 【第27回】SimuTrans OTRPで関東+αを再現
- 「東京シャトル」乗車レポート
- 「THE アクセス成田」(深夜便)乗車レポート
- 18きっぷで行く東北遠征2025(5日目/乗りバス編)
- 「スーパーレールカーゴ」を撮る!